「カラオケでビブラートがかけられたら、もっと上手く聴こえるのに…」
そんな悩みを抱えていませんか?
自然なビブラートは、歌声に深みと感情を与え、聴く人の心を惹きつけます。
しかし、自己流で練習しても「震えすぎて不自然」「全然かからない」など、思うようにいかない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、初心者でも短期間でビブラートを習得できる具体的な練習方法を、段階的にわかりやすく解説します。
「歌がうまくなりたい」「ボイトレに興味がある」「カラオケで上達を実感したい」そんなあなたに、今日から始められる実践的なメニューをお届けします。
ぜひ最後までご覧ください。
1. ビブラートとは?歌唱に欠かせない表現技法
ビブラートの基本定義
ビブラートとは、音程や声の振動を細かく上下に揺らすことで、歌声に表情や感情を加える歌唱技法のひとつです。
クラシックやオペラだけでなく、J-POPやカラオケなど、幅広いジャンルで使われています。
特に日本では、カラオケ採点でも「ビブラート加点」があるため、上達したい人には欠かせない技術です。
ビブラートの特徴は、「一定の周期で規則正しく音程が揺れる」こと。
手で音波を描くようなイメージで、自然な揺れを作ることが理想です。
なぜビブラートが歌に効果的なのか?
ビブラートをかけることで、歌声に以下のような効果が生まれます:
- 声が伸びやかに聴こえる
→ 声の揺れがロングトーンを自然に聴かせてくれる。 - 感情表現が豊かになる
→ ビブラートの深さや速さで、切なさ・優しさ・力強さなどを表現できる。 - 音程のブレをカバーできる
→ 多少の音程のズレがビブラートで自然に聴こえることも。
また、プロの歌手のような「余裕のある歌声」に近づく効果もあるため、ボイトレ(ボイストレーニング)でも重要な項目として指導されます。
ビブラートの種類
ビブラートにはいくつかの種類があります。
初心者がまず目指すべきは「ナチュラル・ビブラート」と呼ばれる自然な揺れです。
以下に代表的な種類を紹介します。
| 種類 | 特徴 | 用途の例 |
|---|---|---|
| ナチュラルビブラート | 声帯・喉の自然な揺れで無理のない発声 | バラードやポップス全般 |
| 喉ビブラート | 喉を意図的に上下に動かす人工的なビブラート | 初心者に多いが不自然になりがち |
| 腹式ビブラート | 横隔膜の動きで揺らすビブラート | 練習すれば安定性が高く自然 |
| 顎ビブラート | 顎を細かく動かして音を揺らす | 一部の演歌や効果音的な演出 |
多くの初心者が最初に身につけるのは「喉ビブラート」や「顎ビブラート」ですが、これは不自然に聞こえる原因にもなります。
本記事では、無理なく自然にかかるビブラートの習得法を解説していきます。
ビブラートは「筋肉のコントロール」でもある
「ビブラート=声の震え」と思われがちですが、実際は声帯や呼吸筋、そして喉や横隔膜など、複数の筋肉が関係しています。
つまり、ただ真似するだけでなく、身体の使い方を理解することが習得のカギです。
とくに、ボイトレでは以下の3つを意識してビブラートを練習します。
- 息の安定(腹式呼吸)
- 声帯のコントロール
- 喉や顎のリラックス
これらは、ビブラートだけでなく、全体的な歌唱力の向上にも直結します。
筋トレのように、少しずつ鍛えるイメージで取り組むと効果的です。
ボイトレの現場でも重視される「脱・無理ビブラート」
多くのボイストレーナーが指摘するのが、「無理やりかけるビブラート」は逆効果だということ。
喉を締めたり、顎を震わせたりして無理に揺らすと、音程が不安定になったり、喉を痛めたりするリスクがあります。
正しい方法で練習すれば、ビブラートは“出そうとしなくても自然とかかる”ようになります。
この記事で紹介するトレーニングを実践することで、自然なビブラートを短期間で体得することも可能です。
ビブラートは習得できる技術
「自分には才能がない」と感じている方も多いかもしれません。
しかし、ビブラートは生まれつきのセンスではなく、身につけられる“技術”です。
プロの歌手でさえ、最初から自然にできた人は少なく、多くがボイトレで練習を重ねて身につけています。
これから紹介する練習法を実践すれば、あなたも「自然なビブラートがかけられる歌い手」になれるはずです。
2. ビブラートがうまくかからない理由とは?
ビブラートを練習しても「不自然になる」「そもそも揺れない」と感じたことはありませんか?
初心者が陥りやすい問題には、共通する原因があります。
この章では、うまくいかない理由を明らかにし、どこから改善すべきかを整理していきます。
原因1:喉に力が入りすぎている
ビブラートがかからない人の多くは、「喉声」で歌ってしまっています。
喉の力で無理に声を出すと、揺れを生む柔軟性がなくなり、声が硬くなります。
チェックポイント
- 高音で喉が締まる
- 歌った後に喉が痛くなる
- 声が前に突っ込む(喉で押す)
この状態では、ビブラートどころか安定した発声も難しくなります。
ボイトレでは「喉を開いてリラックスする」ことが基本で、特に腹式呼吸と脱力が重要です。
原因2:腹式呼吸ができていない
ビブラートには、一定の息の流れが不可欠です。息が細くなったり、ブレたりすると、安定した揺れは生まれません。
特に、胸式呼吸の癖が強いと、横隔膜がうまく使えず、揺れが途切れてしまいます。
こんな人は注意
- 歌っている最中にすぐ息切れする
- 息を吸うと肩が上がる
- 声が細くて伸びない
腹式呼吸をマスターすると、声の支えが安定し、ビブラートも自然にかけやすくなります。カラオケ上達を目指すなら、まず呼吸法の見直しが必須です。

原因3:音程が不安定なまま揺らそうとしている
ビブラートは「音を安定させた上で、意図的に揺らす」技術です。
しかし、そもそも音程が定まっていないまま揺らそうとすると、ただの不安定な声に聴こえてしまいます。
特にありがちなのが
- 音が定まらず、ピッチが揺れているだけ
- 音程を維持しようとすると喉に力が入る
- 自分では揺れているつもりでも、聴くと伝わらない
これは「ピッチ(音程)を支える筋肉」が鍛えられていないサイン。
まずはスケール練習などで音程の安定を図りましょう。
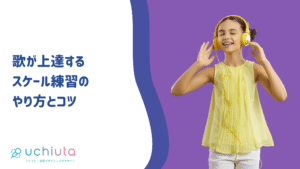
原因4:ビブラートを「喉や顎で揺らす」癖がある
YouTubeなどで「ビブラートの真似」をしていると、喉や顎を物理的に動かすクセがつきやすくなります。
これは一見揺れているようで、音質的には非常に不自然です。
よくある悪い例:
- 顎を上下に動かして「ウィーンウィーン」と揺らす
- 喉を震わせて、意図的にブレさせる
- 小刻みに震えて早すぎる揺れになる
これらは「癖ビブラート」と呼ばれ、上達の妨げになります。
正しいビブラートは「声帯と呼吸の連動」によって生まれる自然な揺れです。
ボイトレでこの癖を一度リセットし、正しいフォームからやり直すことが大切です。
原因5:音を伸ばす基礎力が不足している
ビブラートは「ロングトーン(長く音を伸ばす)」ができないと始まりません。
たとえば「ア〜〜〜〜〜」と声をまっすぐに保ちながら、後半に自然な揺れを加えるのが理想です。
しかし、以下のような人は要注意です。
- ロングトーン中に音が揺れてしまう
- 息が足りず途中で途切れる
- 音が震えて安定しない
まずは、まっすぐに声を伸ばせるようにしてから、ビブラートを練習するステップが王道です。
原因6:耳(聴覚)が育っていない
意外と見落とされがちですが、「自分の声がどのように揺れているか」を聴き分ける力も重要です。
聴覚が育っていないと、自分ではかけているつもりでも実際にはかかっていなかったり、逆に不自然に聴こえたりします。
改善法
- スマホ録音で自分の声をチェックする
- 上手な歌手のビブラートを真似する
- カラオケ採点機能を活用する
「聴く力」を鍛えることで、自分のビブラートを客観的に調整できるようになります。
原因分析のまとめ
初心者がビブラートをうまくかけられないのは、単に技術不足というよりも「基礎力」と「身体の使い方」に原因があることがほとんどです。
ビブラートは派手なテクニックに見えますが、実は地味な基礎練習の積み重ねが不可欠なのです。
次章では、誰でも今日から始められる、効果的なビブラート練習方法をステップ形式で紹介していきます。
3. ビブラートを自然にかける練習法
ビブラートを自然にかけるには、正しい順序と意識が重要です。
感覚任せで身につけようとせず、「基礎を整え、身体の使い方を理解し、段階的に揺れを身につける」ことが上達への近道になります。
ここでは、初心者でも自宅でできるビブラート習得の練習法を5ステップで紹介します。
ステップ1:腹式呼吸と脱力の徹底
まず取り組むべきは「呼吸と脱力」。
ビブラートに限らず、すべての発声の土台になる部分です。
練習メニュー:
① 腹式呼吸練習(1日5分)
- 仰向けに寝て、お腹に手を置く
- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹が膨らむのを感じる
- 口から細く長く「スーーー」と吐き出す(10秒以上目標)
② 脱力確認
- 鏡の前で肩・首・顎に力が入っていないかをチェック
- 首を左右にゆっくり回し、力を抜いて発声の準備をする
ポイント:
脱力状態で声を出す感覚がつかめないと、ビブラート以前に発声が不安定になります。
ステップ2:まっすぐなロングトーンを出す練習
ロングトーンはビブラートの土台です。
「揺らさず、まっすぐに伸ばす」ことを意識して練習しましょう。
練習メニュー
① ロングトーン(5〜10秒を目標)
- 母音「あ」や「う」で「アーーーーー」「ウーーーーー」と発声
- 息のスピードを一定に保ち、声が揺れないように注意
- できるだけ喉に力を入れず、息の支えで音を伸ばす
② 録音チェック
- スマホで録音し、音が一定かどうかを確認する
- 揺れている場合は、支えが弱いか息が不安定になっているサイン
ステップ3:ピッチコントロールと音程の安定
音程が定まっていないと、ビブラートの揺れが不自然に聴こえてしまいます。
この段階では、スケール練習や半音の上下運動を取り入れましょう。
練習メニュー
① 半音スライド練習
- 「アーウーアーウー」のように、半音または全音の上下を滑らかに繰り返す
- ピッチがブレないよう、正しい音程を意識する
- ゆっくり→早く、というふうにテンポを変えて練習
② キーボードやチューナーを活用
- キーに合わせて音程のずれを確認する
- カラオケのピッチバーを使うのも効果的
ステップ4:ビブラートをかける練習(基礎編)
いよいよビブラートの実践練習です。
まずは「意図的に揺らす感覚」をつかむところから始めます。
練習メニュー:
① 息の揺らしでビブラートの基礎感覚を掴む
- ロングトーン中に息の量を少し増減させて、声に軽く揺れをつける
- 「ア〜〜〜〜(ふわふわ揺れる)」と小さく一定に揺らす
② ピッチを意図的に揺らす
- 半音程度の上下を「アーウーアーウー」とリズム的に揺らす
- 4拍→8拍→16拍と細かくしていき、自然な揺れに変える
③ 頻度を一定に保つ(メトロノーム練習)
- メトロノームに合わせて1秒間に5〜6回程度で揺らす感覚をつかむ
- 揺れの速さがバラバラにならないように注意
ステップ5:自然なビブラートに仕上げる(応用編)
ここまできたら、声にビブラートを「乗せる」感覚に進みます。意識せずに出せるようになるのが目標です。
練習メニュー
① 歌に取り入れる
- ゆっくりしたバラードなど、語尾が伸びるフレーズを選ぶ
- 例えば「未来へ〜〜〜(揺れる)」のように、語尾だけを軽く揺らす
- 最初は「1フレーズに1回」だけ使うのがおすすめ
② 表現に合わせた使い分け
- 切ない表現:ゆっくり深いビブラート
- 軽快な表現:細かく浅いビブラート
- 同じ揺れ方ばかり使うと単調になるため、曲の雰囲気に合わせて変化をつける
ビブラート習得のための補助アイテム・環境づくり
自宅ボイトレにおすすめの環境:
- 防音カーテンや吸音材で、安心して発声できる空間を作る
- 録音できるスマホアプリやオーディオインターフェースがあると◎
- メトロノームやチューナーアプリも活用
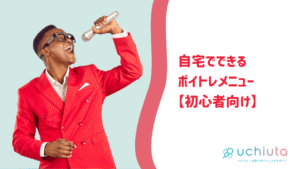
ビブラート習得における注意点
- 喉や顎を無理に動かす「癖ビブラート」はNG
- 揺らそうとしすぎて声が震えるのは逆効果
- 「揺れる」のではなく「響きが広がる」感覚を目指す
自然なビブラートは「響き」と「支え」から生まれる
最終的に、ビブラートは「声が響く状態」と「息が安定して支えられている」ことの結果として自然に生まれます。
共鳴腔を意識し、身体全体で響きを感じながら練習することで、無理のない美しい揺れが身につきます。

ビブラートの種類を意識する
ビブラートには、揺れの幅や速さによって「タイプ」があります。これを使い分けることで、歌の表現力は格段にアップします。
主な3タイプ:
| タイプ | 特徴 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 深くて遅いビブラート | 揺れ幅が大きく、ゆったりしたテンポ | バラード、感情のこもったフレーズ |
| 浅くて速いビブラート | 揺れ幅は小さく、テンポが速い | ポップス、リズミカルな曲 |
| 波形ビブラート(均等) | 揺れ幅・速さともに一定 | ジャズやクラシック、安定感を求める時 |
コツ
録音して客観的に聞いてみると、自分のビブラートの「癖」が分かります。自分の声質に合ったビブラートタイプを見つけましょう。
プロのビブラートを聴いて分析する
プロ歌手のビブラートを聴くことで、「揺れ方」「入れ方」「強弱のつけ方」を学べます。
おすすめの分析ポイント
- 語尾のどのタイミングで揺れ始めるか?
- 揺れの速さは均等か?変化があるか?
- フレーズのどこにビブラートを使い、どこで使っていないか?
コツ
好きなアーティストの「一音だけ」ビブラートを真似する練習から始めると、コツがつかみやすくなります。
感情に合わせて“かけない勇気”も持つ
ビブラートは「常に使えば良い」わけではありません。
- 歌い出しはストレートなロングトーン
- サビで感情を乗せてビブラートを加える
- 曲の終わりで余韻として揺らす
このように、「引き算の表現」を意識すると、ビブラートがより効果的に聴こえます。
上手いビブラートとは、単に揺れている声ではありません。
聞き手に感情が伝わる“必然の揺れ”であることが、プロとアマチュアの違いです。
あなたの声に、あなたの思いを乗せて揺らす。
それが本当の意味で“自然なビブラート”です。
4. よくある質問
まとめ – ビブラートは練習すれば誰でも習得できる!
「ビブラートをかけたいけど、うまくできない…」「練習しているのに自然に聞こえない…」
そんな悩みを抱えるのは、あなただけではありません。
実は多くの人が、最初はうまくいかずにつまずいています。
しかし、正しい練習方法と基礎の積み重ねがあれば、誰でも自然なビブラートを習得できます。
この記事で紹介したように、
- 安定したロングトーンの発声
- 息のコントロール(腹式呼吸)
- 音の揺れ幅とスピードの調整
- 曲調に合わせたビブラートの使い分け
これらを一歩ずつ練習していけば、確実に声は変わります。
大切なのは、一気にできるようになろうと焦らないこと。
毎日の少しの練習の積み重ねが、やがて大きな成果になります。
録音して自分の声を聴き返すことで、客観的に成長を確認できますし、改善点も見つけやすくなります。
もし「今日はうまくいかなかったな」と思っても大丈夫。
それもまた、上達への大切な一歩です。
ビブラートは独学でも習得可能ですが、ある程度練習しても「なんだか不自然」「音が揺れすぎてしまう」などの壁にぶつかることがあります。
そんなときは、プロのボイストレーナーから客観的なアドバイスを受けるのがおすすめです。
「独学で頑張ってきたけど、あと一歩が難しい…」
そんなあなたは、ぜひ一度プロのトレーナーの力を借りてみてください。
今よりもっと自由に、魅力的に歌える自分に出会えるはずです。










