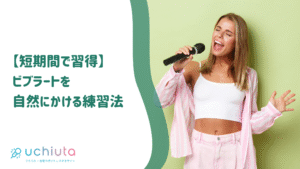「なんだか声がこもって聞こえる」「もっとスッと通る声で歌いたい」
──そんな風に感じたことはありませんか?
実は、声が通らない原因は発声や共鳴のコツを知らないだけ、ということが多いんです。
この記事では、声をしっかり響かせて通るようにするためのポイントを、初心者にもわかりやすく解説します。
カラオケでもっと上手に聞かせたい方、音程が不安定な方にも役立つ内容なので、ぜひ参考にしてください。
1. 基礎知識 – 声が通る仕組みとは
「声が通る」ってどういうこと?
「声が通る」とは、単に大きな声を出すことではなく、少ない力で遠くまでしっかり届く声のことを指します。
カラオケやライブでマイク越しに聴いてもクリアに響く声には、共通する発声の特徴があります。
それは、「響き(共鳴)」と「正しい声の通り道(声道)」を活かしているということです。
発声の基本:呼吸・声帯・共鳴の連携
声は、大きく3つのステップで作られています。
- 呼吸(ブレス):息を吸って吐く力が「声のエネルギー源」となります。歌の場合は、特に「腹式呼吸」が重要です。
- 声帯振動:息が喉にある「声帯(せいたい)」を通ることで振動し、音になります。
- 共鳴(響き):その音が口、鼻、胸などの空間に響いて、「通る声」として広がります。
これらがうまく連動していないと、「かすれた声」「こもった声」「通らない声」になりやすいのです。
共鳴腔(きょうめいくう)って何?
「共鳴腔」とは、声が響く空間のこと。主に以下の3つがあります:
- 咽頭腔(いんとうくう):喉の奥にある空間。
- 口腔(こうくう):口の中。母音の響きに大きく関係します。
- 鼻腔(びくう):鼻の奥の空間。高音の響きや倍音に関係。
これらの空間を適切に開き、響きをコントロールすることで、声が通りやすくなります。
倍音とは?声の「厚み」と「抜け」に関係する秘密
「倍音(ばいおん)」とは、声の中に含まれる複数の周波数成分のこと。
人の声は、基本の音(基音)に対して倍の周波数を持つ音が重なっており、これが「厚み」や「抜け」のある声の秘密です。
例えばプロのシンガーの声が「よく通って聴きやすい」と感じるのは、この倍音が豊かに含まれているから。
トレーニング次第で、倍音の多い声に近づくことも可能です。
声が通らない人の共通点とは?
以下のような特徴があると、声が通りにくくなります:
- 喉に力が入りすぎている
- 息のコントロールができていない(浅い呼吸)
- 口の開きが小さく、共鳴腔が狭い
- 声帯がうまく振動していない
これらはトレーニングで改善できるため、原因を知ることで効果的な練習につながります。
2. 問題と原因の分析
1. 喉に力が入りすぎている
多くの初心者がやってしまうのが、「大きな声を出そう」とするあまり、喉に力を入れて押し出すように声を出すこと。
この状態では、声帯がうまく振動せず、声がかすれたり、響きが弱くなったりします。
声が通るためには、「喉を脱力」し、「響かせること」に意識を向ける必要があります。
ポイント:声は“出す”より“響かせる”
2. 呼吸が浅い/息の支えがない
発声の土台は「呼吸」です。特に浅い胸式呼吸しかできていないと、息の量が足りず、弱々しい声になりがちです。
腹式呼吸ができると、しっかりした声が出せるだけでなく、安定した音程や声量のコントロールも可能になります。これは、声を響かせる“燃料”を安定供給できている状態です。
3. 口の開きが不十分
声の響きには「口の形」も大きく関係します。口がしっかり開いていないと、音の出口が狭まり、こもった声になります。
また、母音が不明瞭になると、聞き手にも伝わりにくくなります。
解決のヒント:母音を意識して、あくびのように口を開けると響きやすくなる。
4. 共鳴腔が使えていない
声が通るためには、「音を響かせる空間(共鳴腔)」をうまく使う必要があります。
たとえば、高音を出そうとするあまり、喉を締めてしまうと、共鳴腔がつぶれて声が響かないという現象が起こります。
共鳴腔をうまく使うには:
- 喉をリラックスさせて開く
- 口の中を「縦に広く」保つ
- 鼻腔共鳴(鼻に抜ける感じ)も意識してみる
こうしたポイントを意識することで、倍音の豊かな、通る声に近づけます。
5. 音程が不安定だと「響き」もブレる
声が響くには、声帯が安定して振動することが大前提です。
音程がぶれると、声帯の振動が不安定になり、結果として響きにくく、通らない声になります。
つまり、「音程の安定」=「通る声の安定」にもつながるということです。
これは、特にカラオケで「音程バーが外れる」と感じる人には重要なポイントです。
6. 声の響きに意識が向いていない
意外と多いのが、「とにかく声を出そう」とするあまり、自分の声がどう響いているかを聞けていないパターン。
共鳴や通る声を出すには、自分の声を「内側からモニタリングする感覚」が必要です。
練習中にスマホ録音などで声をチェックすることで、客観的に「通る声」かどうかを確認できます。
3. 解決策と具体的な練習方法
ステップ1:腹式呼吸を身につけよう(基礎)
目的:安定した声の土台を作る
効果:ブレない声・安定した音程・余裕ある声量
やり方:
- 仰向けに寝転がり、お腹に手を置く
- 息を吸って、お腹が自然に膨らむのを感じる(胸はなるべく動かさない)
- 口から細く長く息を吐く(10秒以上を目指す)
ポイント:慣れてきたら立った状態でも実践しよう。肩が上がるのはNG。
注意点:無理に息をたくさん吸おうとすると逆効果。リラックスを第一に。
ステップ2:ハミングで共鳴感覚をつかむ(導入)
目的:共鳴腔に響きを乗せる感覚を養う
効果:鼻腔共鳴・声の抜け・倍音が増える
やり方:
- 口を閉じて「ん〜」と小さく声を出す(ハミング)
- 鼻の奥・顔の中心(マスクの内側)に響きを感じるように意識する
- 声を上げ下げして、響くポイントを探す
ポイント:顔がビリビリする感覚=共鳴ができている証拠。
注意点:喉に力を入れず、軽く出すこと。低めの音から始めるとやりやすい。
ステップ3:リップロールで喉をリラックスさせる
目的:声帯の脱力・息の流れを整える
効果:喉を開いた発声・滑らかな音程変化・通る声の基礎作り
やり方:
- 唇を軽く閉じ、「ブルルル…」と息を吐いて震わせる
- 声を加えて「ぶるるる〜」と音階をつける(ドレミファ〜のように)
- 最初は低音から中音、高音へと無理なく上げていく
ポイント:リップロールが安定しないときは、指で両頬を軽く押さえるとスムーズになる。
注意点:声を張らずに、息の流れに乗せて自然に行うこと。
ステップ4:母音トレーニングで響きを整える
目的:母音ごとの響きを明確にし、共鳴腔の使い方を習得
効果:こもらない発音・口腔共鳴の強化・声の抜けが良くなる
やり方:
- 「ア・エ・イ・オ・ウ」を一音ずつ、ゆっくり丁寧に発声
- 各母音の響きの場所を観察する(例:「イ」は前方、「オ」は奥)
- 鏡を見ながら、口の開き方・舌の位置をチェック
ポイント:「ア」は縦にしっかり、「イ」は横に軽く広げて発音すると、響きが明確になる。
注意点:口の動きをサボらないこと。特に「ウ」「イ」はこもりやすいので要注意。
ステップ5:発声練習で「通る声」を育てる
目的:これまでの感覚を統合し、実戦的な声に近づける
効果:通る声の習得・倍音の増加・歌唱力の向上
やり方:
- 「あー」のロングトーン(10秒キープ)をゆっくり繰り返す
- 音程を変えて「ド〜ソ〜ド〜」のような3音スケールで発声
- ハミング→母音→発声へと段階的に移行していく
ポイント:録音して自分の声をチェックすることで、響きの成長を実感できる。
注意点:疲れてきたらすぐに休む。無理して喉を壊さないことが最重要。
応用編:カラオケで実践してみよう!
日常で練習成果を試すなら、カラオケが最適です。
以下のような曲を選ぶと練習効果を実感しやすくなります:
- 音域が広すぎないミドルテンポの曲
- メロディがシンプルで、言葉がはっきりした曲
コツ:原曲キーにこだわらず、自分の出しやすいキーに調整するのが成功の秘訣です。
4. よくある質問
まとめ
声がこもる原因とその改善方法を紹介してきました。
ポイントは、「声を出そう」とする前に、正しい呼吸・響きの感覚・喉の脱力を身につけること。
声は“力で出すもの”ではなく、“響かせて育てるもの”です。
すぐに劇的に変わるわけではありませんが、
1日5分の腹式呼吸やハミング練習からでも、確実に変化は訪れます。
筆者自身も、最初は自分の声が嫌いでしたが、共鳴の感覚を身につけてからは、「声が前に出ているね」と言われることが増えました。
ぜひ、今日紹介した練習を一つでも取り入れてみてください。
小さな実践の積み重ねが、あなたの“通る声”を確実に育ててくれます。
しかし、「やり方が合っているか分からない」「自分だけでは改善点に気づけない」
そう感じる場面もあるかもしれません。
そんなときは、プロのボイストレーナーに見てもらうという選択肢もおすすめです。
実際、筆者も独学で行き詰まっていたとき、体の使い方や共鳴のポイントを直接指導してもらうことで一気に視界が開けました。
特に「声の通り方」や「音程の安定」などは、自分では気づきにくいクセが原因になっていることも多いため、客観的なアドバイスが大きな助けになります。
「もっと上手くなりたい」「自信を持って歌いたい」と思ったときが、学びどきです。
無理せず、自分のペースで。
あなたの声は、もっと伸びます。