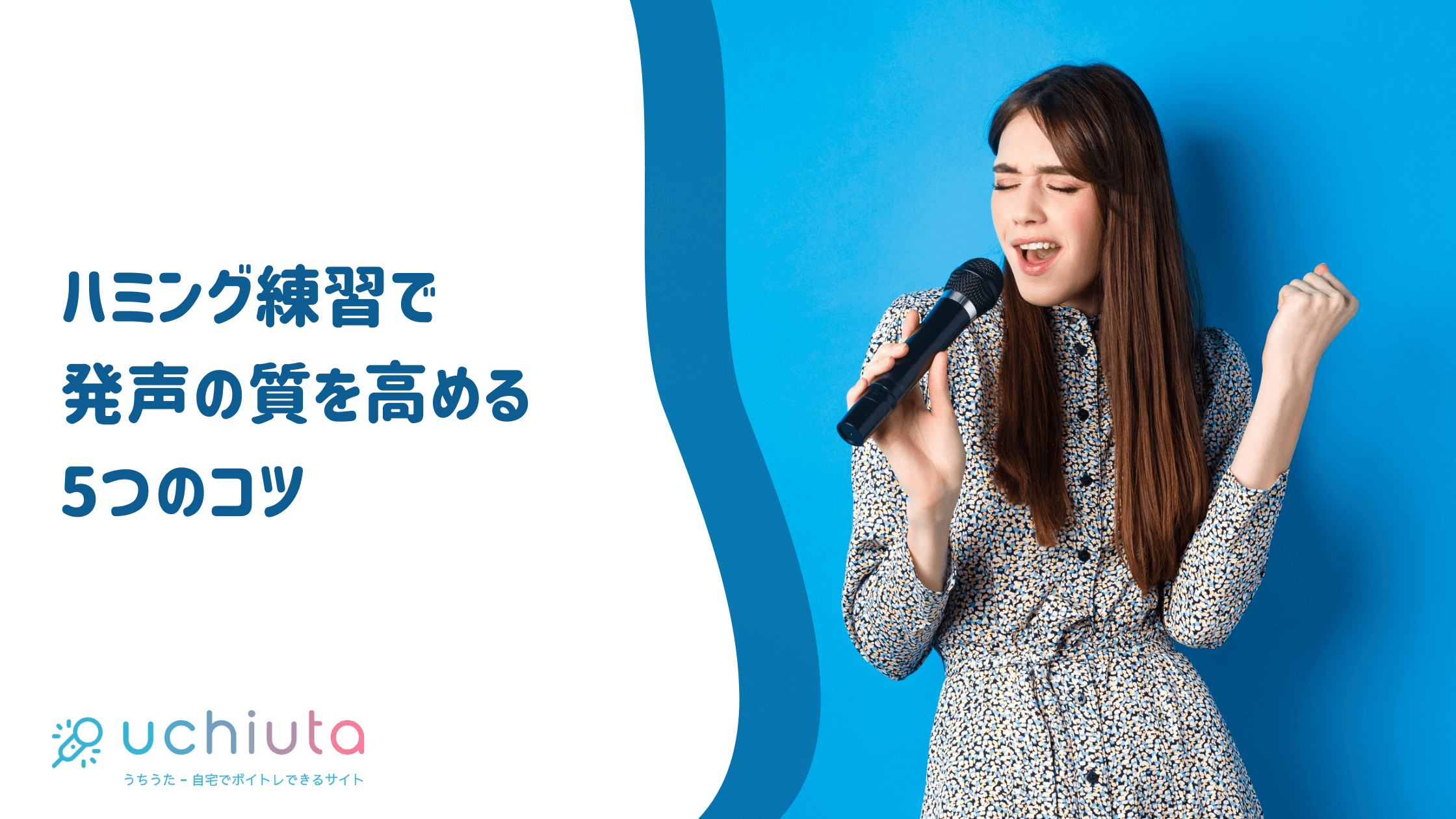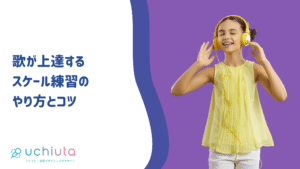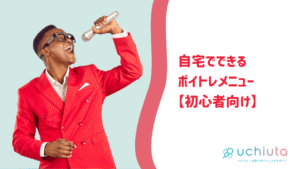「ハミングって、ただ鼻歌を歌うだけでしょ?」そう思っている方は多いかもしれません。
しかし実は、ハミングはプロの歌手も取り入れる重要なボイトレ(ボイストレーニング)法のひとつ。
発声が安定せずに「カラオケで音が外れてしまう」「声がかすれてしまう」と悩んでいる方にこそ、試してほしい練習方法です。
本記事では、初心者でも今日から始められるハミング練習の基本とコツを5つに分けてわかりやすく解説します。
声帯の負担を減らしつつ、歌唱力を無理なく伸ばせる方法を知れば、きっと歌うことがもっと楽しくなりますよ。
これから歌を上達させたい方や、自宅でできる手軽なボイトレを探している方は、ぜひ最後までご覧ください。
1. ハミング練習とは何?「鼻歌以上、発声未満」の優秀トレーニング
「ハミング」とは、口を閉じたまま鼻に響かせて声を出す発声方法のことです。多くの人が無意識にやっている鼻歌も、れっきとしたハミングの一種です。
ただし、ボイトレにおけるハミングは単なる鼻歌とは違い、発声の質を高めるためのトレーニングとして活用されます。特に以下の点で重要です。
- 声帯を無理なく使える
- 響き(共鳴)を体感しやすい
- 自宅でも静かに練習できる
つまり、ハミングは喉に負担をかけずに、正しい発声の基礎を身につけるための最適な練習法といえます。
なぜハミングがボイトレに効果的なのか?
ボイトレ(ボイストレーニング)では、「いかに無理なく、通る声を出すか」が基本です。
ハミングはそのための最初のステップとして非常に優れています。以下の理由があります。
1. 声帯の繊細な動きを意識できる
ハミングは声を張る必要がなく、微細な声帯の動きを感じやすくなります。
とくに初心者は、大きな声を出す前に、まず「小さく丁寧な声の出し方」を身につけることが重要です。
2. 声の共鳴(響き)を体感できる
口を閉じて鼻に響かせることで、頭の前面(鼻腔や額)あたりに振動を感じることができます。
これが「共鳴」の感覚で、後の発声練習や歌唱にも活かされます。
3. 喉にやさしく、負担が少ない
無理に大声を出さずにすむため、喉を傷める心配がほとんどありません。
特に、カラオケで声が枯れやすい人や、発声に自信のない初心者に最適です。
ハミング練習で得られる5つのメリット
ハミングを習慣にすると、歌やボイトレにどんな良い影響があるのでしょうか? 以下のようなメリットがあります。
- 発声の土台が安定する
声の出し始めから安定し、ブレのない音程が取りやすくなります。 - 音程感覚が鍛えられる
ハミングでは耳と感覚を頼りに音を取るため、音程をコントロールする力が自然と養われます。 - 鼻腔共鳴を活かした“通る声”に近づける
ハミングで共鳴の感覚をつかむことで、声がこもらず遠くまで届くようになります。 - 日常生活にも取り入れやすい
周囲に迷惑をかけず、時間も場所も選ばずにできるのがハミングの魅力。習慣化しやすく、継続にも向いています。 - カラオケの歌唱力アップに直結する
声帯のコントロール力と音程の精度が高まることで、自然と歌がうまく聞こえるようになっていきます。
ハミング練習の種類と基本姿勢
ハミングにもいくつか種類があり、目的に応じて使い分けが可能です。
| ハミングの種類 | 特徴と目的 |
|---|---|
| リラックスハミング | 息と声を優しく出す。ウォーミングアップ向き。 |
| 口閉じハミング | 共鳴を強く意識。共鳴練習や音程練習に適している。 |
| リップロール+ハミング | 唇を震わせながら声を出す。喉を開く練習として有効。 |
基本姿勢は、背筋をまっすぐ伸ばして、肩の力を抜くこと。
そして、鼻から息を出すように「ん〜」と響かせるだけでOKです。
難しいテクニックは不要なので、初心者でも安心して始められます。
2. ハミング練習がうまくいかない理由
「ハミングがいいって聞いて始めてみたけど、あまり効果が感じられない……」
そう感じて途中でやめてしまう方も少なくありません。
実は、多くの初心者が共通してつまずくポイントが存在します。
ここでは、ハミング練習がうまくいかない代表的な原因と、その背後にある「問題点」を3つの視点から分析します。
1. 響きを感じられない=共鳴ができていない
よくある状況
「ん〜」と声を出しているつもりでも、鼻や顔の前あたりに振動や響きがまったく感じられない。
主な原因
- 声の出し方が喉に偏っている(喉声)
- 息がうまく流れていない(呼吸が浅い)
- 姿勢や口の形が不自然になっている
解説
ハミングの最大の目的は、「共鳴(響き)」の感覚を養うことです。
しかし、喉だけに頼った発声では、音が鼻腔に響かず、共鳴も感じられません。
これは「喉声(のどごえ)」と呼ばれる状態で、ボイトレにおいては改善すべき発声の代表例です。
また、鼻が詰まっていたり、息の流れが不十分だと、声が共鳴腔に届かず響きが弱まります。
2. 息のコントロールが不安定=ブレる音程・不安定な発声
よくある状況
- ハミングの音が途中で「ふっ」と消えてしまう
- 音程がふらついて安定しない
- 一音をまっすぐ保てず「揺れる」感じになる
主な原因
- 腹式呼吸ができていない
- 息を吐く量や圧力が一定でない
- 姿勢が崩れていて肺が十分に使えていない
解説
ハミングは息をコントロールしながら声を出す訓練です。
安定した息がなければ、音も安定しません。
とくに「音がすぐに消える」「伸ばせない」場合は、息の支えが足りない証拠です。
また、音程のふらつき=音痴に聞こえる最大の原因。これは、音感だけでなく息の流れの乱れでも引き起こされます。ボイトレで「息の支え」を重視するのはこのためです。
3. 継続できない=変化を感じる前にやめてしまう
よくある状況
- 数日やって「効果がない」と思ってやめる
- 他の練習法にすぐ浮気してしまう
- モチベーションが続かない
主な原因
- 目的が不明確なまま始めてしまっている
- 成果を判断する基準がない
- 変化がすぐに見えづらい練習法である
解説
ハミングは地味な練習法です。**1回やっただけで劇的に歌がうまくなる、という即効性はありません。**だからこそ、目的や目標を明確にしないと、途中でやめてしまいやすいのです。
また、成果を実感するまでにはある程度の「継続期間」が必要です。
たとえば、毎日5分の練習を1ヶ月続けると、確実に声の出しやすさ・響きの質・音程の安定感に変化が出てくるという実例も多く報告されています。
「よくある勘違い」にも注意!
初心者がやりがちな誤解も、練習効果を妨げる原因になります。
| 勘違い | 正しい理解 |
|---|---|
| ハミングは小さな声だから意味がない | 小さな声でも声帯・共鳴・呼吸の連動が鍛えられる |
| 音程を意識しなくていい | むしろ音程意識が大事。無意識だと悪い癖が残る |
| 自分の声が聞こえないから上達していない | 「振動を感じる」=成長のサインと捉えるべき |
私の体験談 – 最初は「響き」なんてわからなかった
私自身もハミング練習を始めた頃、「これで本当に効果があるのか?」と半信半疑でした。
鼻に響かせるといっても、最初はどこに響いているのか全然わからず、ただ声を出しているだけのように思えました。
ところが、毎日5〜10分、姿勢と息に気をつけながら丁寧に続けるうちに、ある日突然「おや?鼻の奥に響いてるかも」という感覚がつかめました。
それ以降は、明らかにカラオケでの声の抜け方や安定感が変わってきたのを実感しました。
さらに後になって、「鼻腔共鳴(びくうきょうめい)」という概念を知ったとき、ハミング練習の鼻に響かせることとつながりました。
3. 今日からできる!ハミング練習5ステップ
ハミングは、正しく行えば声帯を傷めず、自然な響きを育てる効果的なトレーニングです。
特に初心者にとっては、発声の土台づくりに欠かせない要素が詰まっています。
ここでは、自宅でも静かにできる「ハミング練習5ステップ」をご紹介します。
1日5〜10分からでも構いません。コツコツと続けることで、声の通り・音程の安定・共鳴感がしっかり身につきます。
ステップ1:基本の姿勢と呼吸を整える
目的
ハミングの効果を最大限に引き出すには、正しい姿勢と腹式呼吸が欠かせません。
手順
- 足を肩幅に開いてまっすぐ立つ(座っても可)
- 背筋をやさしく伸ばし、肩の力を抜く
- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹をふくらませる
- 口を閉じて「ん〜」と声を出しながら、お腹をへこませつつ息を吐く
ポイント
- 声が「鼻の奥」に響くように意識
- 息を吐くスピードは一定に保つ
- 力まず、自然体で行う
注意点
喉に力が入ると響きがなくなるので、喉がリラックスした状態で出すのがコツです。
ステップ2:低音で安定した「ん〜」を出す
目的
声帯への負担を避けながら、共鳴の基礎を作る
手順
- 先ほどの姿勢と呼吸で、低めの音程で「ん〜」と声を出す
- 響きを「鼻の奥」「前歯の裏」「おでこのあたり」に感じる
- 5秒〜10秒、一定の音で伸ばす
ポイント
- 振動を感じる部位を意識(共鳴腔)
- 録音して聞くと音の揺れが確認できる
- 共鳴を感じるまで繰り返す
注意点
音程がぶれやすいので、1つの音を保ち続けることを意識しましょう。
ピアノアプリやキーボードで基準音を確認しておくと良いです。
ステップ3:音の上下をつけたハミングスライド
目的
音程感覚と声のスムーズな移動(滑らかさ)を養う
手順
- 中音から始めて「ん〜♪」で上下に音程をスライド
- 例:「ん〜♪↑(高く)↓(低く)→もとの音へ」
- 上下に音をゆっくり往復(1セット5秒×3〜5回)
ポイント
- ヒュッと上げ下げするより、なめらかに滑らせるように
- 喉ではなく、息の流れで音程を調整する意識で
- 口は閉じたまま、響きを鼻腔に保つ
注意点
無理に高音を出そうとすると喉が締まりがち。出しやすい範囲で行うのが大切です。
ステップ4:母音ハミング(口を軽く開けて響きを拡張)
目的
鼻腔だけでなく、口腔内(口の中)まで響きを広げる感覚を身につける
手順
- 「ん〜」から口をすこし開けて「ん〜あ〜」と発声
- 徐々に「ん〜い〜」「ん〜う〜」など他の母音も試す
- 各母音に2〜3秒ずつかけて切り替える
ポイント
- 「ん〜」の響きを保ったまま母音に移ること
- 喉ではなく響きで母音を出すイメージ
- 声を鼻→口へ自然につなげるように
注意点
口を大きく開けすぎると、響きが鼻から抜けてしまいます。口の開け方は控えめに、響きを優先しましょう。
ステップ5:メロディハミング(実践編)
目的
実際の歌に近い形でハミングを使い、音程・リズム・共鳴を連動させる
手順
- 簡単な童謡や知っている曲をハミングで歌ってみる
- 歌詞はつけず「ん〜ん〜ん〜」だけでメロディをなぞる
- 録音して音程や響きのブレを確認
ポイント
- 例:「キラキラ星」「チューリップ」などゆっくりした曲が◎
- 音程が外れそうなところは、何度か繰り返して練習
- 呼吸のタイミングも意識して区切る
注意点
音程に集中しすぎると喉に力が入りがちなので、必ず「響き」を優先して練習しましょう。
練習を習慣化する3つのコツ
- 毎日決まった時間にやる(例:歯磨き前後)
→習慣になりやすく、無理なく継続できる - スマホの録音で変化を記録する
→最初との違いに気づけるとモチベーションが上がる - 無理に長時間やらない
→1日5分でもOK。継続の方が重要
この練習メニューを2週間〜1ヶ月続けることで、多くの方が「カラオケでの声の抜けがよくなった」「音程のズレが減った」といった実感のある効果を得ています。